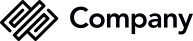中小企業の賃上げ、課題を克服し成功させるための戦略
【中小企業必見】賃上げ課題を克服する戦略
近年、日本経済の活性化には、賃上げが不可欠だと盛んに叫ばれています。特に、日本企業の大多数を占める中小企業の賃上げは、経済全体への影響も大きく、重要な課題となっています。中小企業の賃上げを阻む要因は複数存在し、その中には、原材料価格や電気代の高騰、コスト増加分の価格転嫁の難しさ、受注の先行きへの不安などが挙げられます。
これらの課題を克服し、持続的な賃上げを実現するためには、どのような戦略が必要なのでしょうか。
こちらでは、中小企業が直面する賃上げの課題を分析し、その解決策、そして成功事例などを紹介することで、賃上げ実現に向けた取り組みを支援することを目的としています。
中小企業が直面する賃上げ課題

景況調査によると、中小企業の業況判断DIは回復基調にあるものの、人手不足感は深刻さを増しています。売上が回復しつつある一方で、それを支える人材の確保が困難な状況が続いており、この二重の圧力が中小企業の経営を圧迫しています。
構造的な労働力人口の減少
少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少は、日本経済全体の構造的な課題です。これまでは女性や高齢者の就業率向上によって補われてきましたが、近年ではその伸びも鈍化しています。こうした状況下では、限られた人材を獲得するための賃上げは、単なるコストではなく不可欠な投資となっています。
防衛的賃上げの実態
2024年度には賃上げ実施予定企業が増加傾向にあるものの、その背景には防衛的な意図が見られます。多くの企業が「業績の改善が見られないが賃上げを実施予定」と回答しており、このいわゆる「防衛的賃上げ」は、人材確保や物価上昇への対応といった外部要因に起因しています。
賃上げ実施の主な理由としては、人材の確保・採用が約7割、物価上昇への対応が5割強となっており、企業の自発的な業績向上策というよりも、外部環境への対応策としての側面が強いことがわかります。
賃上げ原資確保の苦悩
最も深刻な課題は賃上げ原資の確保です。多くの中小企業が「特に対応はしていない(収益を圧迫している)」と回答しており、賃上げが企業の収益構造を悪化させる恐れがあります。対応策としては「人件費以外のコスト削減」や「製品・商品・サービスへの価格転嫁」が挙げられますが、いずれも容易ではありません。
特に価格転嫁については、取引先との力関係や市場競争の激化により、思うように進まないケースが多く報告されています。コスト削減についても、長年の経営努力によりすでに可能な限りの削減を進めている企業も少なくなく、新たな削減余地を見出すことは困難です。
このように、中小企業の賃上げは、経営上の判断というより、人材確保や市場環境への適応といった生存戦略としての性格が強まっています。持続可能な賃上げ実現には、こうした構造的課題への包括的な対応が求められています。
人材育成が賃上げ課題の解決に与える影響

中小企業にとって賃上げは喫緊の課題ですが、単に賃金を引き上げるだけでは企業の負担が増すばかりです。持続可能な賃上げを実現するためには、人材育成を通じた労働生産性向上という視点が不可欠です。人材育成は、コストではなく企業の将来を左右する戦略的投資と捉えるべきでしょう。
一人あたり労働生産性の飛躍的向上
社内でのスキルアップ研修や資格取得支援などを通じて、既存社員の多能工化・高度化を促進することで、一人あたりの業務効率を大幅に高められます。特に中小企業では、少人数で多様な業務をこなす必要があるため、従業員の能力向上が労働生産性に直結します。例えば、製造現場での多能工化により、一人で複数工程を担当できるようになれば、人員配置の柔軟性が高まり、全体の生産効率が向上します。
優秀人材の定着と企業価値向上の好循環
充実した人材育成制度は、従業員のモチベーション向上や優秀な人材の定着率向上にも寄与します。人材の流出を防ぐことで、育成投資の回収が可能になるとともに、長期的な視点での組織力強化につながります。
また、従業員のスキルアップは顧客満足度の向上にもつながり、企業価値を高めるという好循環を生み出します。高い技術力や対応力は市場での差別化要因となり、付加価値の高い製品・サービスの提供を可能にします。
中長期的視点での人材育成戦略
人材育成は即効性のある対策ではありませんが、中長期的には企業の競争力を根本から強化する取り組みです。短期的な賃上げ対応に追われがちな中小企業こそ、将来を見据えた人材育成戦略が重要です。
経営資源の限られた中小企業では、すべての施策を一度に実施することは困難かもしれません。しかし、自社の強みや課題を見極め、優先順位を付けた人材育成の取り組みを継続的に行うことで、持続可能な賃上げの実現につながる基盤を構築できるでしょう。
無料相談で始める賃上げ課題解決の第一歩
賃上げを実現したいと考えながらも、原資の確保に苦慮する経営者は少なくありません。この課題の根本にあるのは「労働生産性の向上」です。日本の実質賃金は1970年以降右下がりの状態が続き、2020年からはマイナス状態が続いています。この背景には労働生産性の停滞があり、OECD加盟国中では24位と低迷しています。賃上げを持続的に実現するためには、まず現状の正確な把握と課題の構造的理解が必要です。
専門的視点から課題を整理する
賃上げ課題は複合的であり、「人件費が高い」という思い込みではなく、「一人当たりの付加価値をいかに高めるか」という視点へ転換することが重要です。無料相談では、以下のような項目について専門家の客観的視点から課題を整理できます。
具体的な行動計画へつなげる
無料相談を通じて得られた課題認識を、具体的な行動計画に落とし込むことが重要です。「KIDA式」などのマネジメント手法を活用し、トップ自らが危機感を持って取り組むことで、短期間で成果を生み出すことが可能になります。特に中小企業では、経営者自身が先頭に立ち、全社的な取り組みとして賃上げ課題に向き合うことが成功の鍵です。
中長期的視点での賃上げ計画
一時的な賃上げではなく、持続可能な賃上げを実現するためには、5年程度の中長期計画が必要です。2022年からの5年間で人件費が約2倍になるという試算を踏まえ、これからも着実に増加が続くことを見据えた計画が必要です。そのため利益率10%以上を目指す経営改革が求められます。無料相談を起点に、自社に最適な賃上げ戦略を構築し、着実に実行していくことで、企業の持続的成長と従業員の豊かな生活の両立が可能になります。
まずは行動を起こすことが何より重要です。賃上げという課題に向き合い、専門家の支援を受けながら一歩を踏み出しましょう。
賃上げ実現への道筋と持続的成長へのステップ
こちらでは中小企業の賃上げ課題とその解決策について詳しく解説してきました。原材料価格の高騰や価格転嫁の難しさといった課題に直面する中小企業が持続的な賃上げを実現するためには、労働生産性の向上が不可欠です。
エムエスアイ研究所が提供する「KIDA式」のアプローチは、トータルプロセス管理や付加価値創出に焦点を当て、企業の利益率向上と賃上げ原資の確保を可能にします。短期的な対策ではなく、人材育成や労働生産性向上という中長期的視点に立った戦略的取り組みこそが、中小企業の持続的な成長と従業員の豊かな生活の両立につながるのです。
賃上げという課題に向き合うには、まず専門家の客観的な視点を借りることから始めましょう。経営者自身が先頭に立ち、全社一丸となって取り組むことで、必ず道は開けます。エムエスアイ研究所では、企業の現状を詳しく分析し、最適な賃上げ戦略の立案をサポートいたします。賃上げを通じた企業価値向上への第一歩を今すぐ踏み出してみませんか。
中小企業の賃上げ課題のご相談ならエムエスアイ研究所
| 名称 | エムエスアイ研究所 |
|---|---|
| ADDRESS | 〒612-8469 京都市伏見区中島河原田町31-1-2-515 |
| TEL | 090-3852-4731 |
| FAX | 075-748-7565 |
| メール | soudan@msi-k.jp |
| URL | https://msi-kaikaku.com |

エムエスアイ研究所 喜田佳弘
INFO
090-3852-4731
soudan@msi-k.jp
ADDRESS
〒612-8469
京都市伏見区中島河原田町31-1-2-515
© MSI研究所